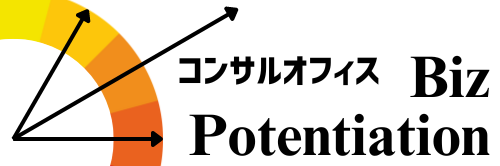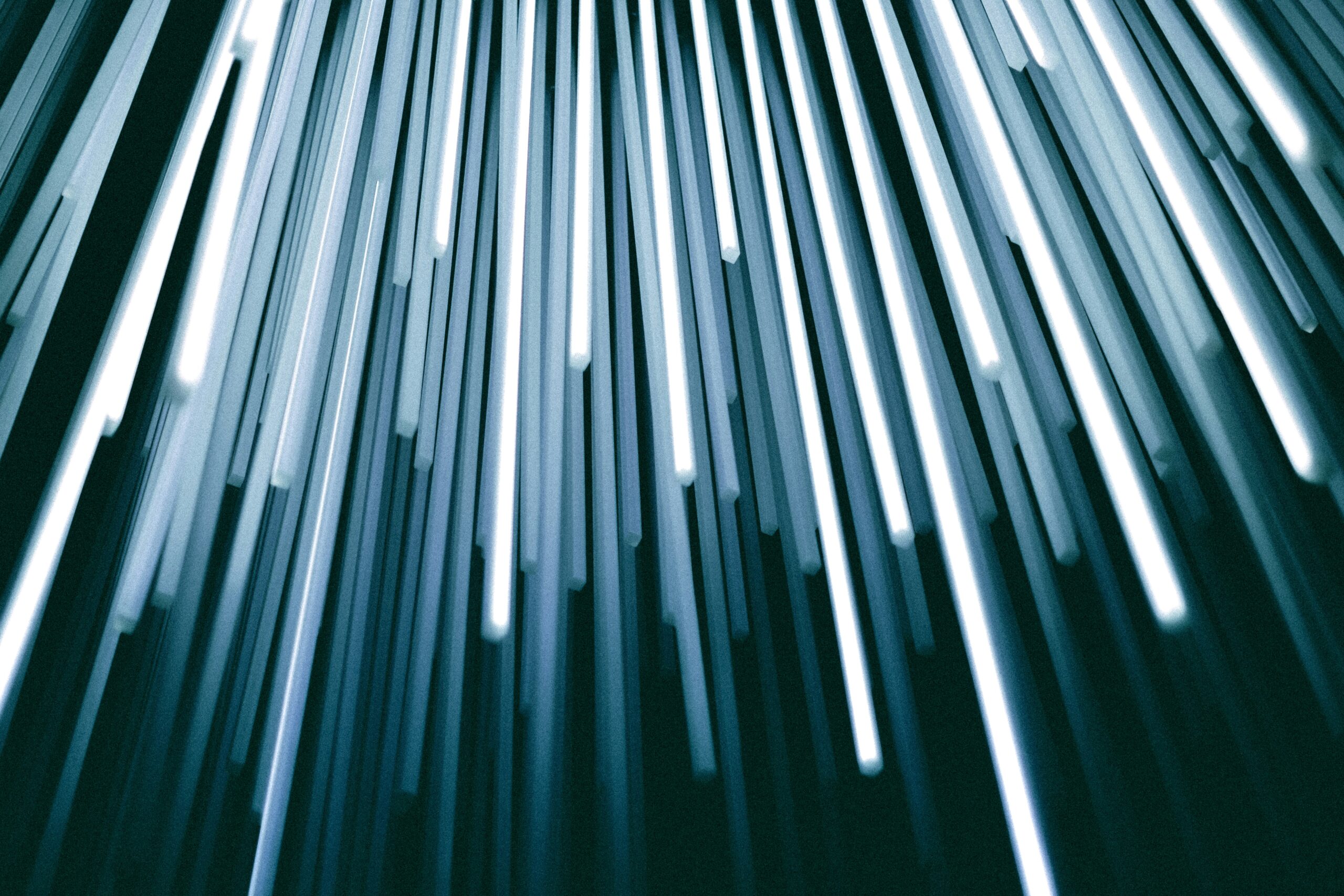(後半で企業の話になります)
昨今のホットなSNS論争
近年、SNSを中心に大きな論争が繰り広げられるのを見る機会が増えたように感じます。
- 2020年ごろから:「ワクチン信奉」対「反ワクチン」
- 2024年-2025年:兵庫県知事の「知事失格」対「知事は巨悪と戦うヒーロー」
これらは過度に単純化された(虚構の、解釈上の)構図であり、そもそもこのように極端に現状を捉えること自体に問題があると私は考えているのですが、その辺はまた後日機会を見て整理したいと思います。
さて、「過度に単純化された」とは書いたものの、実際にこのような対立構造を強く意識して情報発信を行っている方も少なくないので、今回はこの対立構造があるとして話を進めます。
対立構造を意識した投稿の共通点
この論争が起きていること自体が大きな社会問題の一つだと認識しており、両極端な意見の発信情報をそれぞれ見るようにしているのですが、その中でふと気づいたところがあります。
「どちらの立場の人々も、同じような言葉で自分たちを高め、相手方を非難している」ということです。具体的には
(相手方を指して/相手方に対する返信の中で)
- 「論理的に物事を考えることができない/苦手」
- 「こんなことも理解できない/知らない」
- 「すぐに信じてしまう/騙されている」
- 「ちゃんと勉強してください」
(自分たちを指して)
- 「しっかり情報収集をしている/学んできた」
- 「論理的に考えれば分かる」 などなど…
論争の本質に関する仮説
これらを踏まえて、ある解釈に行きつきました。
納得すると同時に、少し驚きました。
彼らが争っているのは「どちらが理知的であるか」という点ではないか?
つまり、「何が正しい結論なのか」はさほど重要な問題ではなく、「こちら側にいる私たちは、『あいつら』よりも優れた存在であるか否か」ということで争っている。
(もちろん、正義感・危機感から発信している人も少なくないでしょう)
また、少し異なる表現で印象的だったものがあります。
- 「(また)あいつらにバカにされる」
これを踏まえて、このように考えました。
これらの論争は、自身の存在価値を守る防衛反応でもあるのではないか?
⇒仮説:SNS論争の背景は、「不安」と「自己防衛(および過剰防衛)」ではないか
【不安】
SNSで積極的に主張を繰り出す背景には、自分自身(の価値)に関する何らかの不安がある
【自己防衛】
①自分が良いと思うものについて、自信・裏付けをつけるために対立するものを批判する
②自分が良いと思うものを頭ごなしに批判されたことに対して反発・反論する
または、③既存の対立構造に対して、より大きな優越感/自己肯定感を得られる側に飛び込む
一度自分の立場を決めてしまったら、なかなか反対側の意見に移ることができない。(既にとったポジションは自分自身の判断結果そのもので、過去の自分を否定することになるためハードルが高い。)
特に上記に挙げた「ワクチン」「政治家の不正・社会巨悪」は一般人が情報を網羅的に収集し尽くすのはほぼ不可能で正確な判断が難しいにもかかわらず、健康や社会を脅かされるリスクがある状況と考えると、誰しも少なからず不安になるのは避けられないでしょう。
自己肯定感を高めるための情報発信が相手方の防衛反応(反発)を招き、双方の対立構造がより悪化するという状況が生まれているのではないかと受け止めています。
企業内でよくある「論争」とは?
前置きが長くなりましたが、この構造は企業の中でも共通する部分があると思い、この記事を書くこととしました。主に部署間の対立や派閥争いです。(経営者から部下にも起こりえます)
この場合の「不安」は、「相手方の部署をよく知らず真の姿を測りかねること」などが考えられます。
「総務の人たちは会社の製品のこと何もわかってないくせに…」
「営業担当って経理のこと全然理解しないで勝手なことするよね」
「文系/理系の人ってさ…」
「研究開発って好きなことを突き詰めたい変な人の集まりでしょ。仕事は趣味じゃないんだから」
「合併前の旧○○社出身のやつは…」
「誰でもできる仕事なのに、何であの部門は給料が高いんだ」
「あの部門の仕事は全部AIにやらせればいいんじゃない?」
大学時代の専攻部門、人事系、経理系、営業系、研究開発系、事業開発系…
同じ企業の中でも、培ってきた知識・経験、考え方も全く違うはずです。
私は製薬企業の研究開発部門から監査法人に転職したとき、周囲の公認会計士やコンサルタントの仕事観に触れる中で、こんなにも仕事観、価値観(働く目的)が違う人がいるのかとカルチャーショックを受けた記憶があります。
全く同じ経験をしていない以上、完全に共感できないのは当然
自身の築いてきた/築いていきたいキャリアそれがどれだけ価値のあるものかは、異分野の方々から簡単には理解できません。価値観を共有していない異分野の畑で働く普通の他人のキャリアが自分のものより魅力的に映るのは(出世・成功などを除いて)まれなケースではないでしょうか。
つまり、他者の背景を過小評価しがちであるということです。
自分のことを十分に理解できない人から軽く見られるのは決して気持ちの良いものではないもので
軽蔑されると無意識的に相手の劣っているところ/自分の優れているところを探して自分を守りたくなってしまうことでしょう。
「違いを理解しよう」の一歩で、お互いに高め合う関係に変われる
他の部門に不満を持つこと自体は避けられませんが、どのような行動に移すかは変えられます。
「相手の立場を尊重する姿勢」や「相手の状況や違いを知ろうとする気持ち」を意識して示したり、相手を理解するための一歩(質問や情報収集)を踏み出すことで、相手からの受け止め方も変わります。自分たちのことを理解してくれようとする人のことは、もっと知りたいと思えるはずです。
関係者同士の相互理解を深めることは、業務上で連携するうえで大きなメリットになります。
社内の風土改善は、ごく些細な取り組みをきっかけに達成できるかもしれません。