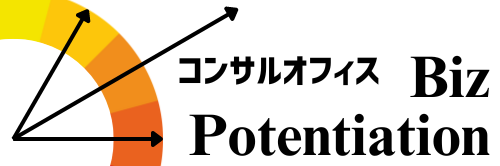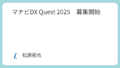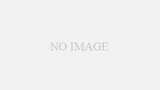はじめに
※本記事記載時点の内容です
高齢化の進展に伴い社会保障費の負担が増大しており、財源の問題から「国民皆保険の危機」と言われて久しいです。
これまで多くの取り組みが進んでおり、特に薬剤費を削る検討が年々進んでおり、2年に一回の価格改定が毎年の価格改定になったり、薬価削減ルールが後付けで次々と盛り込まれたりと、特に製薬業界・薬剤費がターゲットになることの大きい問題です。
ここに最近注目を集めているのが、「OTC類似薬」の取扱いです。
令和7年6月13日、「経済財政運営と改革の基本方針2025 ~「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ~」(骨太方針2025)が閣議決定されました。
この中で、「OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し(※医療機関における必要な受診を確保し、こどもや慢性疾患を抱えている方、低所得の方の患者負担などに配慮しつつ、個別品目に関する対応について適正使用の取組の検討や、セルフメディケーション推進の観点からの更なる医薬品・検査薬のスイッチOTC化に向けた実効的な方策の検討を含む。)」と記載されたことからにわかに注目を集めています。
(追記)2025年の参議院議員選挙において、日本維新の会が「社会保険料を下げて暮らしを変える」とマニフェストの中でうたっており、その中に「OTC類似薬の保険適用除外」と明記されている(なお、特設サイトトップページでは「市販類似薬の保険適用見直し」という表現)ことからも、注目を集めているようです。
OTC類似薬ってなに?
様々な使われ方をしますが、分かりやすさを優先して一言で表現すると
「医療用の医薬品のうち、ドラッグストアなどで同じ有効成分の薬を購入できるもの」です。
風邪薬、花粉症の薬、痛み止め、胃薬など様々です。
OTC医薬品ってなに?
ドラッグストアなどで購入することができる薬のことです。
なぜ、こんなに話題になっているの?
①国全体にとって金額のインパクトが大きいから
国民医療費は45兆円を超えており、これは対GDP比で8%を超えています。⇒国民医療費の概況
総額、対GDP費比共に伸び続けており、一般会計歳出の1/3を社会保障費が占めています。⇒一般会計予算
人口減少社会では高齢者の割合が高くなり、医療費をどう抑制していくかはずっと悩みの種になっていくと思われます。
②医薬品の価格差が大きく、患者にとって金額のインパクトが大きいから
保険で使われる医薬品は価格が決められていて、毎年強制的な価格見直し(値下げ)が起こります。
そのため、医療機関で処方される時の価格はとても安いです。赤字状態にあるような製品もあります。
反面、OTC医薬品は製薬会社が自由な価格をつけて販売することができます。
同じ有効成分を同じ量含んだ薬であっても、十分な利益が確保できる価格設定がなされるため、OTC医薬品はOTC類似薬(医療用医薬品)と比べてとても高額になります。具体例をいくつか見てみます。(有効成分と含有量、ブランド名が同じものを基準にして、商品は任意に選択しています)
OTC医薬品はテレビCMも許可されているので、一般的な知名度も大きいですね。
アレグラ(フェキソフェナジン):抗ヒスタミン薬
| 分類 | 商品名等 | 価格(記事記載時点における、薬価または希望小売価格) |
| 【医療用、先発】 | アレグラ®錠60mg | 26.1円/1錠(10割負担の場合) |
| 【医療用、ジェネリック】 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「●●(会社名等)」 | 10.4円~23.1円/1錠(10割負担の場合) |
| 【OTC】 | アレグラ®FX | 68.8円~103.3円/1錠当たり (1,446円/14錠、3,850円/56錠) |
ボルタレン(ジクロフェナクナトリウム):消炎鎮痛テープ
| 分類 | 商品名等 | 価格(記事記載時点における、薬価または希望小売価格) |
| 【医療用、先発】 | ボルタレン®テープ15mg | 12.7円/1枚(10割負担の場合) |
| 【医療用、ジェネリック】 | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg | 11.5円/1枚(10割負担の場合) |
| 【OTC】 | ボルタレンEXテープ | 123.8円~146.6円/1枚あたり (1,026円/7枚、2,599円/21枚) |
医療用医薬品は3割負担だとさらに安く、上記の0.3倍の自己負担になります。
ただし医療機関を受診する場合、実際の患者負担額はこれに加えて様々な料金(≒診療報酬)がかかります。初診料/再診料、各種管理料、検査料、処方箋料、調剤料、各種加算、などなど…
医療機関は小売店と違い、薬の仕入れと販売の差額の儲けは少ないため、これらの診療報酬が主な収入にあたります。
③医療機関にとってもインパクトが大きいから
花粉症などの慢性疾患では、極端に言うと「薬をもらうために病院に通っている」という人も少なくはないでしょう。
患者さんの求める薬が病院で処方できなくなる、または通院する価格メリットがなくなると、薬をもらうために通院する必要がなくなります。
病院や薬局にとっては、収入源である診療報酬が発生するお客さんが来なくなってしまうわけです。
お金のためだけではありません。患者さんの健康への悪影響も懸念されています。
後述しますが、患者さんのための診療を行う上で困ることもたくさん出てきます。
もしも、OTC類似薬の保険外しという世界が到来した場合…
この骨太の方針を踏まえて具体的にどのような対策が行われるかは不透明ですが、
この記事では極端な例として「社会保障費削減の目的で、慢性疾患薬を含む一部のOTC類似薬が突然保険診療で使えなくなったら?」という世界を考察してみます。
(上の注記にもある通り、こんな極端な変化はすぐには起こらないと思われます。保険診療外しは、こどもや慢性疾患患者を直撃する可能性があるためです。)
OTC医薬品は薬局でも買うことができますが、ドラッグストアで購入するものと仮定して進めます。
【OTC類似薬の保険外しによるメリット】
- 医療費・社会保障費が削減できる
- 薬剤費が減る(薬剤の処方料がそのまま減った場合)
- 受診自体が減ると、薬剤費だけでなく診療報酬・調剤報酬が発生しない
- 通院を削減できる場合、病院と薬局への通院の手間が減る
- セルフメディケーションに対する社会的な意識、国民の医療リテラシーが高まる可能性がある
- 軽度な受診が減少し医療現場の人材不足が緩和される
【OTC類似薬の保険外しによるデメリット】
- 患者の経済的負担が増える(上述)
- 薬を入手する手間が増える(病院と薬局⇒病院と薬局とドラッグストア)
- 医師や調剤薬局の薬剤師は、「OTC医薬品を買って使ってくださいね」というしかなく、薬の購入状況や使用状況、副作用を把握することが難しくなる
- 実際には患者さんは薬を購入しないかもしれないので、次回の診療時の服用状況確認が難しくなる
- 患者さんが勘違いして別の薬を買ってしまったり、より良い薬だと思って医師の意図と異なる薬を買ってしまう可能性がある
- 具体的な薬の用法・用量も患者さんにしか分からない(一日1回の薬か、3回の薬かは買ったOTC医薬品によって違う)
- 薬の副作用や効果について、医師や薬剤師が認識できなくなるリスクがある
- 処方薬とOTC医薬品の相互作用(併用注意など)の確認が行いにくくなる
- 調剤薬局の薬剤師やドラッグストアの薬剤師や登録販売者は、(医師が処方したい医薬品の全体リストが見えないため)診察内容や投薬の意図の理解が難しくなり、適切な案内を行いにくくなる
- 薬の使い方や注意点について理解が不十分なまま使い続けてしまうリスク(保険に基づかないのでカルテがなく、お薬手帳を見せて購入するわけではない)
- 正しく使わないと、作用が弱まったりする薬もある
- 使いすぎると、体の別の場所に副作用を起こしてしまう薬もある
- 自己判断で、過剰な量を購入して使ってしまうリスクもある
- 自己判断による治療の浸透によって、SNSなどで独自の医療解釈を生み、国民の医療リテラシーがむしろ低下する可能性がある
- 保険診療で入院患者に使える薬の選択肢が減る
- 患者さんの治療を把握・管理するために処方薬のシフトが起き(OTC類似薬⇒新しい薬)の処方が増え、医療費があまり減らない(むしろ、増える)可能性もある
- OTC類似薬と同様の効果をもつ、比較的新しい医療用医薬品薬を処方して患者さんの治療状況を可視化したいというインセンティブが働く
- 新しい薬は薬価の値下がりが十分に進む前であったり、ジェネリック医薬品がなかったりするので、OTC類似薬よりも高くつく場合が多い
- 来院が減ると医療機関の収入が減る(廃業の場合、医療体制崩壊の可能性)
患者目線では、OTC医薬品は高すぎて治療をためらう可能性もある
特に慢性疾患では毎日使うような薬もあるので、経済的な負担は非常に大きくなります。
仮に、3カ月に一度通院し、ジェネリック含めて薬局に4,000円支払っている場合、これがOTC医薬品に切り替わるといくらの負担になるのか、上記の薬の例からも相当な負担の増加になることはイメージできるかと思います。
(どの薬剤で試算するかによって結論の恣意性が高くなってしまうので具体的な数字は省略します)
いざドラッグストアの店頭に行って、「こんなに高いのか…」と治療を諦めて健康を犠牲にしてしまう人も出てくるかもしれません。
OTC医薬品が割高な理由は色々と挙げられます。
- 医療保険では値段の圧力があり、「病院の薬が安すぎた」という見方もある
- 医療保険で薬価が下がっている分、十分な利益を確保するための強気の価格設定
- テレビCMをはじめとする大規模な広告宣伝費の価格への上乗せ
OTC医薬品への価格介入はあるのか?
OTC類似薬の保険外しが行われた際、政治家の意図したとおりのOTC医薬品へのシフトが起こるかという際、一つのネックになるのがOTC医薬品が割高であるということです。
自由な市場競争に基づくものなので、この価格に介入することは本来許されないことですが
もしもこの重大な禁忌を破ってOTC医薬品がグッと値下がりすれば、医療費の削減効果もそれだけ大きなものになるでしょう。もしかすると、OTC類似薬の保険外しをする必要すらなくなるかもしれません。
しかし、国による直接的なOTC医薬品市場への介入は果たして認められるのでしょうか…?
業界を超えた甚大な影響が懸念されます。
また、OTC医薬品の値段が劇的に安くなると
海外への輸出目的での大量購入や、不適切な使用目的での購入などのリスク、結果として適正流通の阻害による医療アクセスの悪化も強く懸念されるところです。
以下は私個人の空想の正解の話になりますが、
もしかすると、「薬価の10割負担」などという未来はあり得るかもしれません(10割負担の場合、現役世代の薬代部分は3.3倍に、高齢者世代の薬代部分は10倍になる)。
OTC類似薬の公定薬価に基づく価格を基準として保険給付率を下げることによって、国が薬の価格に介入してOTC医薬品ほどの患者負担を避けつつ、社会保障費(薬剤費部分)が抑えられるという可能性は
それでも以下の問題点は残るので、OTC類似薬の問題の解決は非常に難しい問題です。
- 保険給付率の高い、より高額な薬価の代替薬へのシフトが進む(逆に医療費が増える)
- 保険の適用される医療と適用されない医療の同時実施(混合診療)は現在禁止されている
- 病院の割安感が残る限りにおいては、受診数(診療報酬)の減少は期待しにくい
まとめ考察
3点のQ&A形式で上記の考察をまとめます。
1.「OTC類似薬の保険外し」という政策は有望なの?
医療費が逼迫していますので、国の財政に注目すれば
医療費を削ろうというアプローチは当然、重要な政策です。
しかし闇雲に実施しては「患者側の受けるデメリットが増えるだけ」という結果にもなりかねません。
自己責任・自己判断・副作用のリスク、出費の増加、医師に治療実態を把握してもらう難易度の増加…
2.「OTC類似薬の保険外し」は医療費の削減につながるか?
国の財政面へ大きな期待をする人も多いでしょうが、「OTC類似薬の薬剤費が医療費のうち1兆円を占める」ことは、「OTC類似薬を保険から外したら1兆円の医療費が削減できる」ということを意味しません。保険から外したOTC類似薬に代わるものを、どこからどのように調達するかの検討が必要だからです。
診察室での医師と患者の診療という関係性においては、OTC類似薬を保険外しするメリットは双方にとってあまりありません。医師は患者の実態をしっかり把握したいですし、患者は自己負担が大きく増えることを嫌がります。
単純に保険外しをするだけでは、「OTC類似薬から乗り換えることのできる代替薬にシフトする」ことが多く、医療費削減効果はほとんど望めない(むしろ増える可能性もある)と考えられます。
3.保険対象外になると、患者の医薬品負担は何十倍にもなるのか?
一部SNSなどでは盛り上がっていますが、こちらも暴論だと思います。
「骨太の方針」の注記を見る限り、何らかの緩和措置が打ち出されると推測されます。
しかし、患者の懸念を政治家に伝えていくことを怠れば、現場を無視した机上の空論、数字だけの試算でひどい政策が実行に移されることもあるかもしれません。
しっかりと現場の懸念や困りごとを発信し、誰もが安心して健康に生活できる中での医療費削減を達成するのは非常に重要なことです。
最後に
単純にOTC類似薬を保険診療で使用できなくなるようにしただけでは、医療費の劇的な削減には直結しないと考えられます。
関係する様々な規制の変更などと合わせ、複合的なアプローチをもとに、患者負担(経済面・健康面)が最小限になる形での変更を期待したいところです。