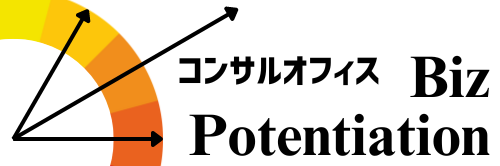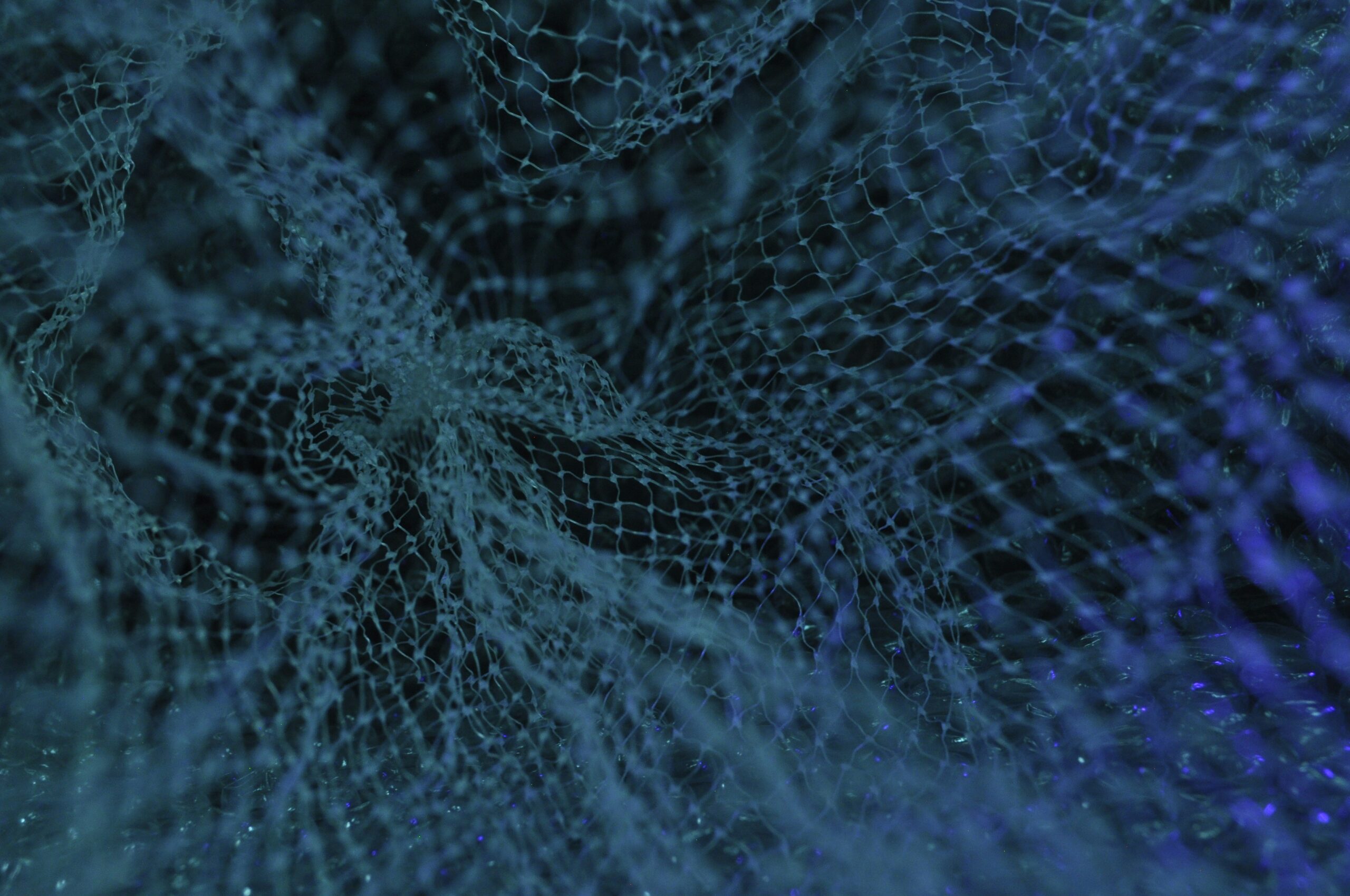はじめに
AIの精度の向上が止まりません。
(今日時点のAIのレベルもすぐに過去のものになってしまうだろうと思いますが)2025年3月末、つい2-3日前、ChatGPTの画像生成のレベルが大きく向上したことが話題になっています。
- 実写の写真をもとに、ジブリアニメ風の画像を出力できるようになった
- 生成された画像中の日本語等の文字の表示精度、画像内の言語の整合性が大きく向上した。
(これまでは「言語っぽい何か」であることも多かった) - 意味のある漫画形式の画像が出力できるようになった
- 出力した画像の一部を変更しながら出力させることが可能になった
(例えば画像中の人物の手の開き方を変える、キャラクターの複数パターンを描画するなど) - などなど…
この記事では、日々進化する生成AIに対して
「中小企業はいつから生成AIを使い始めるべきか?」について記述していきます。
結論:すぐに始めたほうがよい。ただ、焦る必要性はそこまで高くない
私の結論から書きますと、「すぐに始めたほうがよい」につきます。
始めるべき理由は単純、とても便利だからです。
上記の画像生成をはじめ、目的を入力してタスクに分解、資料構成のたたき台作成、スペルチェック、複数のウェブ検索によるレポート作成など、ここには到底書ききれませんが、思いつく仕事はAIに聞くと想像以上の回答をしてくれるでしょう。
なぜ「焦る必要性はそこまで高くない」のか
最も大きいのは、いわゆる先行者利益があまり大きくないと考えられるのが理由です。他には、品質・環境が流動的であり、保守的な風土が強い場合になじみにくいことも挙げられます。
生成AIの活用においては「プロンプトエンジニアリング」、つまりどのように指示・依頼を出すかというコツがアウトプットに非常に重要であると言われて久しいですが
生成AIの精度が格段に向上し続けている現在では、生成AI側の進歩が、ユーザー側の「コツ」を大きく超えてきている現状があります。不定期的に、すべてのユーザーが少し先のスタートラインに自動的に連れていってもらえるような状況が生まれています。AIの精度が大きく向上するたびに、皆が手探りでそのAIの使い方を学んでいくことになります。
もちろん生成AIへの習熟度が高い方がうまく使いこなせることは間違いありませんが、決定的な先行者利益と言えるほどかというと疑問が残ります。
生成AIの利活用は「まさに今、AIを使うメリットそのもの」を基準に考えてもよいかもしれません。
「すぐに始めたほうがよい」というのは変わらない
焦る必要性は高くないと述べたばかりですが
もし仮に先行者利益がゼロだったと仮定しても
「まさに今、AIを使うメリットそのもの」自体がとても大きいです。
最初は仕事に限らず、プライベートな相談もよいきっかけになります。
明日の夕食の献立をどうしよう?
週末は何して過ごそう?
仮にうまくいかなくても、キーワードを追加したり意図を追加説明してみるとコツがつかめてきます。
ぜひ一日も早く、生成AIを活用してみてください。